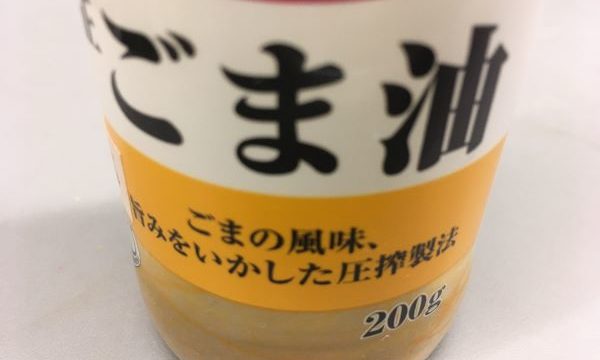春はそら豆の季節ですね。
副菜やビールなどのおつまみにも楽しめて、食卓があかるくなります。
でも調理する際には、そら豆の薄皮と外側のさやを食べていいのか?悩んでしまう人も多いですよね。
そこで今回はそら豆の皮は、そもそも食べられるのか?さやは捨てるだけなのか?について紹介します。
そら豆の皮って食べるの?
そら豆の皮は食べられるの?といわれれば、食べられます。
また、そら豆の外側の皮にあたるさやは、調理法などによっては美味しく食べられるんですよ。
新鮮なそら豆の薄皮は、ナマのままでも食べることができ、その食感はクセになる美味しさがあり、お酒のつまみにもなります。
我が家でも後に紹介するやり方で調理して、薄皮ごと食べますよ。
子供はちょっと苦手みたいなんですが、皮はむけますのでそのまま調理しています。
それに、そら豆は薄皮ごと食べたほうが豊富な食物繊維も摂取でき、体への効能が期待できますから捨てるのがもったいないんですよね^^;
ただ、そら豆の鮮度が落ちると薄皮の固さが増し、食感が悪くなるため、薄皮ごと食べる際には、できるだけ鮮度の良いものを選んで調理するのがオススメです。
そら豆の皮の食べ方
我が家でそら豆の皮を食べる時には、「焼く」「茹でる」といった調理法をで美味しく食べてます。
・そら豆の焼き方

そら豆を最も簡単に美味しく食べる方法は、さやごと焼いて、皮が黒く焦げ付くまでじっくり焼くと、そら豆の旨みを逃すことなく美味しさが凝縮されます。
焼いたそら豆は、熱いうちにさやの中から取り出し、薄皮ごと食べられます。
焼きそら豆が初めての人であれば、薄皮を剥いて食べてみれば、その美味しさは格別ですので、試してみるのをオススメします。
・そら豆の茹で方

そら豆を茹でる際には、鍋にたっぷりの湯を沸かし、お湯の量に対して2%程度の塩を入れておきます。
茹でる直前にそら豆をさやから取り出して、湧いた湯の中に入れて茹でます。
お湯に塩を入れておくのは、そら豆に含まれる葉緑素やクロロフィルの劣化を防いで、味を良くするためで、忘れないようにしてくださいね。
茹でたそら豆を水にさらすと味が落ちてしまいますので、少し固めの状態まで茹でたら、お湯から引き揚げ、粗熱をとっておきます。
そら豆は、リゾットやパスタ、炊き込みご飯、味噌汁などのさまざまな料理に利用できます。
リゾットやパスタには塩茹でしたそら豆を利用し、炊き込みご飯や味噌汁にはさやから取り出したそら豆を水洗いして使ってくださいね。
そら豆の茹で方と焼き方を覚えておけば、さまざまな料理に活用ができるので、チャレンジしてみて下さい。
※そら豆の薄皮を利用しない場合には、粗熱をとった豆の皮に軽く切れ目を入れて、豆を取り出して料理します。
そら豆の皮が固い時の茹で方
そら豆は鮮度によって薄皮が固くなってしまうので、皮が固い時には前述したような茹で方にひと工夫を加えます。
茹でる前の下処理として、さやから取り出したそら豆をきれいに洗い、豆のヘタの部分に縦にハサミなどで切れ目を入れておきましょう。
あとは、前述したように、たっぷりのお湯に2%程度の塩を加えて沸騰したら、切れ目を入れたそら豆を入れます。
こまめにアクを取り除き、菜箸でさして柔らかくなったら、お湯から取り出して粗熱をとります。
薄皮の固いそら豆には、茹でる前に切れ目を入れるひと手間を加えることで薄皮ごと食べることができますのでぜひ試してみてくださいね。
そら豆の皮の栄養素
そら豆には、タンパク質、鉄分、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、葉酸、カリウムといった栄養素が含まれています。
また、皮とさやに食物繊維が含まれています。
そら豆に含まれる栄養素には、体の肉となるタンパク源としての効能をはじめ、血液改善効果、代謝機能の向上や疲労回復、免疫機能や抗酸化作用など、さまざまな効能が期待できます。
特に、そら豆の皮やさやに含まれる食物繊維は、腸内の清掃効果が期待でき、便通を良くするため、ダイエットや便秘にも効果がありますよ。
でも、そら豆の食物繊維のほとんどが、さやと皮の部分に含まれていますので、皮をむいて食べる場合には食物繊維のほとんどが摂取できないんですよね。
とはいえ、皮がなくても、そら豆には食物繊維以外の栄養素のほとんどは含まれているため、複数の栄養素による効能が期待できますよ。
栄養素の多くが水溶性であるため、素早く茹でたり調理するのが重要です。
おわりに
今回は、そら豆の皮が食べられるのかや栄養素についてご紹介しました。
そら豆の皮は食べられますが、どんな調理法にせよ、鮮度を落とさないように早めに食べてくださいね。
旬の味覚を楽しみましょう!
では最後までお読みいただきありがとうございました。